(二)
《醒世姻縁伝》が世に出て以来、ある者は、本書は、知る人ぞ知る、史上五本の指の中に入れるべきだと “屋烏の愛”的にべた褒めする。また単なる恐妻家を描いた物語だ、と、云う者もいる。これもまた、あまりに早計な見方ではないかと思うのである。では、いったいこの作品をどのように評価すべきなのであろうか。
中国の封建社会では、長い長い歴史の過程とともに、その封建イデオロギーは中国社会のすみずみまで相当頑強にしみわたっているが、封建倫理観がまずその一つで、儒教でいうところの三綱五常、つまり君臣、父子、夫婦の道の三綱。仁、義、礼、智、信の人の常に守るべき五つの道徳という五常。これが、階級を統治する上で封建社会における道徳の教条となっている。つまり“夫の妻に為す綱領”如きもの、つまり“嫁(とつ)がなければ父に従い、嫁いでは夫に従い、夫死しては子に従う”、“婦女の守るべき徳義、言葉遣い、身だしなみ、閨房でのたしなみを含めた内助の功など家庭内での規律規範を厳守する”こと、と、婦女に対して男子を絶対的支配の地位に置いているのである。
宋代以降明代に至るまで、理学、道学が盛んに提唱されたが、性の道徳観に至っては、婦女への束縛がいっそう際立ち、婦女にとっては重い足かせ、婦女は籠の中の鳥という存在であった。家庭問題、婦女の問題は、当時のひときわ大きな社会問題となっていたのである。《醒世姻縁伝》は、ちょうど《金瓶梅》の後に続いて出た作品で、《金瓶梅》同様、こうした婚姻問題を題材にしており、一家庭を描写の中心に置いた長編小説である。しかも薛素姐がこの小説の中心人物であることから、作品を評価するに当たっては、まずはともあれ、彼女について、おおざっぱでも、分析しておかねばならない。
素姐は、狄希陳と結婚する前までは、美貌で、しかも心根の優しい純真正直な女の子であった。しかし、婚礼の前日になって、作者は、素姐の心の臓が、突然、取り換えられてしまったという荒唐無稽と思える大胆な描写をするのである。して結婚後は、夫を憎悪するように変身させ、更に、作者の筆は留まらず、素姐を思いのまま夫をいびり虐める気性の荒い悍馬のような女にまで変貌させていく。例えば、牢獄と称して閉じ込める、棒で叩く、真っ赤に焼けた炭を襟の隙間から背中に入れる、靴底を刺し子縫いにする針で身体のいたるところをチクチクとやる、口で希陳の腕の肉ひと塊を噛み切る、泰山参詣の際には、下男に代えて、希陳にラバのたずなを牽かせるなど、素姐の夫希陳に対するこうした乱暴狼藉極まる“悪行”こそ、みな一つの問題、妻の方が思い通りに夫を凌虐し、すべて自分のやりたい放題にやってのける。つまり、前述の“夫の妻に為す要綱”を、逆手にとって語っているわけである。
作者の筆鋒は、素姐のこうした悍馬的女の描写だけに留まらず、食べたいものは食べる、着たいものは着る、やりたいことは何でも思い通りにやる、目上の者の言いつけにはわざと逆らい、騒ぎを起こしては、秩序を乱し、それが死ぬの生きるのという争いまでに進むという具合に、何ごとにも拘束されない自由奔放さを素姐に求めていることにまで及んでいるのである。
更に、礼節孝行などについて、道学の先生たちは、“餓死することは小さいこと、礼節を失うことこそ一大事”などと公言するが、素姐は、同様に、それをフンと鼻でせせら笑う。それは、彼女には彼女なりの考えがあってのことなのである。本文の例を見てみよう:
「夫がいなくなったって、天下の後家さんが飢え死にしたなんて聞いたことはないし、あたしはクソ後家なんか通す気はございませんよ!」(訳者注:河南本・第52回P489)
封建社会、ことに明代にあっては、賢者を表彰する風潮があり、いわゆる孝行息子や貞節な婦女を顕彰するための牌坊(牌楼)が大々的に建てられたが、素姐はこれをまったく無視するのである。第52回には、薛教授夫妻が素姐に、孝行息子とその嫁の牌坊を見に行くように言うくだりがあるので、引用してみよう:
|
素姐:
|
「二人で行きなさいよ! あたし行かない!」
|
|
薛夫人:
|
「お父さんがわざわざ見に来るようにって、知らせて来たんじゃないか。何で行かないんだい?」
|
|
素姐:
|
「お父さんの気持くらいあたし、よく分かってますよ、何で呼んだかね。あたしは孝婦なんかになれやしないし、そんな表彰門なんてバカバカしい! あたし、自分の脚に肉があったって、人肉汁なんって、真っ平。犬にでも食わせてやった方がましよ。馬鹿げた話よ!」
|
と、悠々として、素姐は母親の言葉も取り合わず、室を出て行ってしまった。(河南本・第52回P493)
と。
もう一つ挙げておこう:
“親不孝に三つあって、その第一は、後継ぎの無いこと”というのが封建社会の孝道であるが、素姐は希陳との結婚後、子を産み、一族の存続を考え、孝道を尽すことなど、まったく考えもしないのに、逆に、なんと財産の相続権を言い立てる。当時の統治階級が宣揚するところの儒教の道徳観、儒学の伝道、人倫の道などは、どれもさまざまな形で婦女子を縛る精神上の首枷と鎖であったが、素姐はこれらすべてに逆らい、
「フン、ズタズタ覚悟なら、皇帝とだってやり合えるよ! 平気さ!」(河南本・第48回P455)」
とまで云うのである。
ただ、ここで指摘しておかねばならないのは、作者の真意は、何も素姐に同情を寄せてのことではなく、あくまで、儒学伝道の擁護から出た描写であって、素姐をこのように凶悪に仕立て上げることによって、こうした悪行は、やがて悪の報いを受けるという一つの典型を描くことをねらってのことなのである。しかし、数百年後、現在の我われに、封建社会にあって、同族支配体制への反抗、夫権への蔑視、婦女の尊厳を獲得せんとする女性像を描き残したことになろうとは、作者は、千にも万にも夢想だにしなかったに違いない。
素姐はあちこちと駆けずり回り、がむしゃらに当たって行くもののどれも阻止されてしまう、結局は、弧の奮闘であり、最終的には失敗に終る。ただこれは、歴史の必然で、彼女の行為行動は、単に盲目的な本能のなせるワザにほかならないのである。しかし、彼女の言動は、実に面目躍如として真に迫り、呼べばすぐにでも紙面から出てきそうだ。封建同族支配体系を目の仇として見なす反逆的な彼女の性格描写は、我らに深い印象を与えるものであり、中国の小説史上、稀に見る作品である。
《醒世姻縁伝》の中で、作者は、封建国家機関たる各役所、各部署の暗黒面、腐敗振りを赤裸々に暴き出して見せる。一つは国家民族の安否を顧みない恥知らずの輩徒、蟻の甘きに付くが如く、地位を求めて奔走し、地位を得ればその地位に恋々とし、ひとたび異変に遭えば豹変し、まるで脱兎のようにさっさと逃げ隠れる輩、例えば、王振、晁思孝などを描く一方、もう一つには、民から貪り、私腹を肥やすために、民の命をまるで雑草のように軽んじ、思うままに殺す官吏役人らの実態を暴露してみせるのである。第10回では、晁源の正妻計氏は、晁源と珍哥に濡れ衣を着せられ、首吊り自殺に追いやられる。裁判沙汰となるものの、晁源は役所の主管官吏の上から下まで銀子を贈って抱き込んでしまう。こうした人命事件の裁判ですら、知県及び配下の役人は、九百三十両もの銀子、純金六十両、罰米二十石を丸々巻き上げるのである。また第94回で描かれる呉氏の自縊事件では、以下の記述があるので引用してみよう:
「代理知県の希陳は、この告訴を受理して、周先生と相談した。周先生曰く:『こうした銭で買った国子監の監生なんて、たいてい大金を持っているものです。こんな不公不法をやって、結髪の妻君を死に追いやるような男だ、もし銭でも出して頭を下げて来りゃともかく、ここは一番、法に照らして命を償わせる、と出てやりましょう。なに、やつに逃げ道はありありやしません。これが奇貨居くべしというやつです。ごっそり頂いてやりましょう。細かいのを少しずつ集めるより勝ること万倍ですからな』」(河南本・第94回P880)
結局、希陳らは、四千何がしかの銀子をせしめることになるが、つまりこれが人命事件の結果なのである。
小説の中では、このように官吏による汚職行為を赤裸々に暴露する記述はかなり多い。例えば、「麻従吾は、淮安州の通判の職にあること八ヶ月であったが、そのうち六ヶ月は、山陽県の代理知県を兼任していた。手段を弄して、治下の百姓より彼らの皮を剥ぎ、骨髄までも搾り取って、八千両という銀子を溜め込んでいた。お蔭で、息子の麻中桂は、だいぶの土地を買うことができ、まず富裕といわれる身分となることができた。」(河南本・第27回P258)、第12回では:「楮刑庁は、伍聖道(小川)が落した、という書類挟みを呈出させて見てみると、罰金判決書は、ゆうに四五十枚はある。金額は、総計すると一万金を下らない。」(河南本・P119)など例は、事欠かないが、狄希陳のような小物、わずか八品官吏の地位にあってすら、公然と誰憚ることなく大胆に、民百姓の銭財を巻き上げるのであるから、一時でも権力を握った高官や宦官の収賄汚職行為は、おして知るべしであろう。
この他、小説では、役所の下っ端役人、官員らの、悪人の先棒を担ぎ、法も神もなんのその、大胆不敵に悪事を働くさまをも暴く。第43回では、刑房書記の張瑞風と死刑囚の珍哥の獄中での姦通を描き、やがて、張瑞風は、火事騒ぎに乗じ、密かに監獄から珍哥を連れ出してしまう。第14回では、珍哥が絞首の罪に問われて後、晁大舎は、役所の主管官吏を銀子で抱き込み、典獄を務める書記に賄賂を贈り、普通、囚人が牢獄で受けるはずのいびられる苦痛を、珍哥は髪の毛一本ほども受けずに済む、それどころか、なんと、獄内に住み心地のよい別棟まで建てさせ、誕生祝の宴を開き、歌を唄い、そら何個だ、はい何個と数当てをやるなどドンチャン騒ぎをする。こうしたこと事態驚くべきことであるが、ところが、これこそ封建社会の真実を描写しているのである。
こうした財を貪り、金のいかんで官爵を授けたり、目に余る悪行のかぎりをつくす役人は、それでもまだ、表向きはまるで民を我が子のように愛する清廉潔白、公正無比の官吏のような顔をし、世間を欺き通そうとまでするのである。娼婦が当然の存在である反面、貞節婦人に与える表彰門もまたより不可欠なものなのである。晁思孝なる男は、正しくこの種の人間として描かれている。彼は数千もの銀子で、時の権勢宦官、王振のツテに依り、もともと華亭知県という身分から、まんまと実入りのよい通州知州という地位をものにしてしまう。第6回を見てみよう:
「晁知県の出立の日は、何人かの郷宦や挙人が餞(はなむけ)を贈り送行したので、晁知県もまずまずの体面を保ったのであるが、府学、県学の秀才たちや四郷の百姓らに至っては、もともと晁知県を恨むこと蛇蠍の如く、疫病神を追い払う呪いもしかねない有様であった。秀才たちは、何の送行の詞帳の贈呈もしないし、民百姓らは、一人として、清廉官員が離任の時に、やるしきたりの『靴を脱がせて遺愛とする』という『脱靴』の行事をやろうといいだす者がなかった。こんなことじゃ、事情を知らない人は、この晁知県という男がどんなに酷く、百姓連中を搾り取ったかなどということは知りもせず、ただわれわれ華亭の風俗人情が薄くて嫌な土地だと思うだろう。しかたがない、われわれで、送別の詞帳を作り、家の子供らを筆頭に学生らの名前を連ねて、儒学の教官から送ってもらうことにしましょうや。彩亭や靴も用意しておいて、我われの家の小作人や作男らを送行の百姓に仕立てて、脱靴のまねごとをやらせようじゃありませんか。郷宦数人はこんな相談をしたあげく、当日になって、一芝居やった上で、晁知県を船に見送ったのであるが、華亭県の人々は、士人も民百姓も、或いは三牲を買って、念願かない有難うございました、と廟にお礼詣でする者がある。或いは皆で銭を出し合って、慶賀の法事を開く者もあれば、晁知県を亡者扱いにして、紙銭を焼く者もいた。また、果たして酢の中に炭火を投じて、厄病祓いの呪いをやる者もあった。ただ口で有難しと念仏を誦える者もあれば、念仏中に南無クソ陀仏!と呪罵の言を混えて誦える男もあった。」(河南本P50)
民百姓は、すでに恨み骨髄であるが、あの『脱靴』の行事の真似事を、あえてさせるという茶番劇まで描き見せる。作者は、このように、虚偽迎合に満ちた官界を暴露するのであるが、その洞察力は深く鋭く、筆力たるや周到で力強い。
作者は、小説の中で、初めから終章まで巧に、官界のさまざまな人物像を配置し、一人ひとり装いをこらし、舞台に登場させ、互いに騙し合う、私腹を肥やす為に不正行為をする、酒色に溺れ破廉恥な行為をする、民百姓の頭上にあぐらをかき、権力を笠に威張り散らす、などこうした魑魅魍魎の醜態図を我われに幾つも見せてくれるのである。作者は、この他、虐げられ、抑圧される下層階級の人々の悲惨な光景をもかなりの章を割いて書き記している。例えば、第31回を見てみよう。
「癸丑(きちゅう)、甲寅(こういん)、丙辰(へいしん)、丁巳(ていし)と連年荒年が続いたのである。粟がまず一石一両二銭となって、貧乏人たちの悲鳴は天に響いた。やがて二両に上がり、それでも止まらず、一石三両となり、三両が止まらず四両にまで高騰した。それも束の間で、五両となり、続いて六両、七両までに至った。大豆、黒豆、高粱も六両を越えた。麦、緑豆は七両八両の間を上下した。初めの頃は、まだ買うことができたが、やがて銀子はあっても買えないという状態になって来た。糠さえ一斗が二銭もするのである。樹皮、草の根もすべて削り取り、掘り尽くして残りない有様である。……毎朝、四つの城門から担ぎ出される死人の数は四門とも少なくても、七八十は下らなかった。人々はバタバタと倒れていき、なんと十家に九家は死に絶えるという惨状!……小さな子供たちは、男も女も捨てられて、通りに溢れていた。人々は、初めは倒れている死人の肉を切り取って食っていただけであったが、やがて強を以って弱を凌ぎ、衆を以って寡を犯し、おおぴらに、生きた人間を殺して食うようになった。それでも、初めのうちは、互いに異姓の者を殺し食っていたのであるが、後には、骨肉を分けた父子兄弟、また夫婦、親戚同志が隙を見ては殺し合って食うようになってきたのである。」(河南本P290〜291)
こうした天災、凶作飢饉に見舞われるの時ほど、貪官汚吏、不正役人は金儲けの機会に恵まれる。第32回をご覧じろ:
「人々の口にすべき収穫もないのに、租税だけは猶予なく、割当てられ、期日を限って納めないと、三十打四十打と責罰する。今では、粟一石が八両にもなっている。後任の知県は、上奏して恩を乞い、京へ漕運する租税の米を銀子に換えて上納めることを求めようともしない。そして、納めないと、男女を選ばず、子供まで牢に入れて、納めるまで責めたてるのである。これは、公の租税であるから知県の勝手にはできない、といえば、それまでであるが、……それを、ひとたび訴状を提出したりすると、道理が立とうと立つまいと、一切受理し、下役を遣わして呼び出し、例の如く、種々の名目で銭を要求する。出頭して裁きを待っていると、各下役連中が銭をねだる。あげく、役所の建物を修理するためと称して、三十両四十両と罰銀に処す。或いは米を罰して銀子に換えて納めさせる。雑穀を罰し、紙を罰し、材木を罰し、すべて銭で代納させる。そして三日を限って納めるよう命じ、四日目になって納めようとすれば、もう許してくれない。……一家の主人がこうして逼られ死んでしまうと、次は、残された寡婦、孤児が死んでいくという結果となり、一家が死に絶えると、家産は後継ぎなし、と認定され値段が決められ、近隣の人に買うことを命ずるのである。常に一つの小事件からどれほどの人たちを連累したか数えきれない。」(河南本P298〜299)
と、これが人を喰う封建社会の実態描写にほかならないのである!
中国の封建社会は、明代中葉になって発展するが、この時期、商品経済の発展に新たな段階が来る。資本主義生産の兆し、芽生えが見え始めるのである。こうした時勢の変化を捉えた市井文学では、例えば『金瓶梅』のような長編小説も出たが、これより少し後に出版されたのが『醒世姻縁伝』であった。
小説の中の第64回、65回では、希陳の同窓生張茂実という男が登場する。この男、これまで学問をやっては来たが、自らしょせんものにならずと、悟り、南京もの、それも仇家の絹地、顧繍と呼ばれる上物の絹織物を扱う店を開く。彼は、店員の李旺と共に、素姐の顧繍への執着につけ込み、希陳からたっぷりと搾り取ってやろうと謀り、一着分五六両の反物で、三四倍もの利を得る。このように狡賢く、儲け主義の商人像を、作者は、巧妙に浮き彫りにするのである。
また、第84回では、狄希陳が成都府経歴官に赴任するに際し、用意しようとした贈物である:
「笏二本に箸四束、櫛と楊枝四本ずつ、みな象牙のものをね。仙鶴、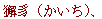 麒麟、斗牛(みずち)の縫いとりを二組ずつ、犀角の帯は、あり合わせの安いものでいいから、これは一本。それより、劉鶴店の上等の合香帯を少々買って行くんです。これなら、上司に差し上げると珍しがられますからね。その他、模様入りの卓布とか、椅子用の敷物、帳子(とばり)など、それから、上掛け、道袍や裙子、袖なしなんかは刺繍入りがいいわね。それと、外套、湖州の鏡、銅炉、模様の入った銅盃、湖州の絹と木綿に松江の綿布眉公布と尺幅綾子、湖州筆、徽州の墨、蘇州の金扇、徽州の白銅鎖と竹編みの名刺入れの小箱、、 麒麟、斗牛(みずち)の縫いとりを二組ずつ、犀角の帯は、あり合わせの安いものでいいから、これは一本。それより、劉鶴店の上等の合香帯を少々買って行くんです。これなら、上司に差し上げると珍しがられますからね。その他、模様入りの卓布とか、椅子用の敷物、帳子(とばり)など、それから、上掛け、道袍や裙子、袖なしなんかは刺繍入りがいいわね。それと、外套、湖州の鏡、銅炉、模様の入った銅盃、湖州の絹と木綿に松江の綿布眉公布と尺幅綾子、湖州筆、徽州の墨、蘇州の金扇、徽州の白銅鎖と竹編みの名刺入れの小箱、、 (ちぢみ)なんか、これらは、書き付けておいて、南京に着いてからお買いなさい。いま流行っているのは、あんたの故郷山東の山繭紬ですから、これも本物かどうかよく見て、十疋ばかりも買って、知府と刑庁さんのお土産になさい。それと、犀角も四つ、お香屋にいいつけて、安息香を二料、それを焚く黄練り炭を二料ばかり作らせなさい。ここ北京では、紗羅の夏靴、天壇鞋を買って、……南京に着いたら、玉でこしらえた上等の簪、かんぬき留め、釦などと翡翠の髪飾り、飾りに使う金糸を刺繍した羊皮を買っておいて、普段の礼物がいるとき、添えて差し上げなさい。」(河南本・第84回P783〜784) (ちぢみ)なんか、これらは、書き付けておいて、南京に着いてからお買いなさい。いま流行っているのは、あんたの故郷山東の山繭紬ですから、これも本物かどうかよく見て、十疋ばかりも買って、知府と刑庁さんのお土産になさい。それと、犀角も四つ、お香屋にいいつけて、安息香を二料、それを焚く黄練り炭を二料ばかり作らせなさい。ここ北京では、紗羅の夏靴、天壇鞋を買って、……南京に着いたら、玉でこしらえた上等の簪、かんぬき留め、釦などと翡翠の髪飾り、飾りに使う金糸を刺繍した羊皮を買っておいて、普段の礼物がいるとき、添えて差し上げなさい。」(河南本・第84回P783〜784)
これは、礼物用の品々の列挙ではあるが、ここから、我われは、当時の手工業工房の専業化、分業化の仔細を、また老舗商品の種類の豊富さを目の当たりにすることができる。
また第79回では、寄姐が食べたがった物が描写されている:
「四川産の蜜桔、福建のおたまじゃくし汁、平陽のさそり、湖広のまむし、霍山の竹狸、蘇州の河豚、大同の黄鼠、固始のガチョウ、莱陽の鶏、 高郵の家鴨の蛋、雲南の象鼻、交趾から入って来る獅子腿、宝鶏の鶏肉、登州の孩児魚。」(河南本・第79回P742) 高郵の家鴨の蛋、雲南の象鼻、交趾から入って来る獅子腿、宝鶏の鶏肉、登州の孩児魚。」(河南本・第79回P742)
こうした品々は、みな各地の名物で、作品の中では枝葉末節、単なる添え物的描写には違いないが、珍しい食べ物の出所、産地が書かれており、当時の商業の発展をかいま見ることが出来る。もはや封建的な自給自足如き自然経済の形態はすでに瓦解、破綻し、各種特産品は商品として、大量に市場に進出しているのである。
資本主義の萌芽を語るもう一つ別の表現形式として見られるのは、小説中に描かれる《銭庄》と呼ばれる“両替商”、それと高利貸しの存在である。両替商は、旧時中国における金融機関の一つであった。初めは単に貨幣の両替のみであったが、両替に止まらず、やがて金の出し入れの仕事を含めた経営をするようになるが、この両替商が、商業資本の発展と高利貸し資本の発展とを互いに固く結び付ける役割をする。例えば、第35回では、増広員生の汪為露を描いている。この男、父親から塾を引き継ぎ、教書稼業をしていたが、やがてこの先生稼業を怠け、金儲けに奔走するようになる。引用してみよう:
「何しろ手元に銭がある。家建物の売買に止まらず、高利の金を貸し、思惑買いをやって稼ぎ賃を取り、人を集めて無尽を起こしたりするようになった。……魂を失ったように夢中になって、東に西にと奔走して、何か安いものがあると聞き込むと、銀子を持って駆けつけて買い入れ、あの品物の値が上がったと聞けば、仲買の家に飛んで行って売り出さなければならない。安い時に買い入れようとすれば、人と先を争い、値上がりの品を売る時は、或いは、まま貸し倒れも免れない。そこで、訴訟を起こすということにもなる。……期限を決め、利子は一割ほどだが、といえば、ハイハイ結構です、決してお手間などおかけしません、期日には持参します、と蜜のような言葉で約束して借りて行く。……喜んだ汪為露は、細君に向かっていうのであった。「銀子があったって、もう土地など買わんぞ、人手はかかるし利子も薄い。金貸しが一番だ。月一割の利子が取れて懐手していりゃいい、向こうから期限にゃ持って来るんだからな。こんなうまい商売は他にはない。」(河南本・第35回P329)
ここの描写で、いくつか注意に値する点を挙げておきたい。
|
1)
|
教師稼業の道を捨て、商いを営む(物価や相場の騰貴と下落をみて利益を得る)。つまり利ざやを稼ぐ商売から、続いて高利貸し、無尽を起こす。これは、前述の張茂実が学問を棄てて、商いを営む、ということと符合するが、同様に当時の社会風潮を語っている。
|
|
2)
|
銭はあっても、土地は買わずに、銭を高利貸しの資本につぎ込む。
|
|
3)
|
高利貸しの資本と商業資本との結びつき(リンク)。
|
こうした情況というのは無論、偶然起るのではなく、社会に起るべくして起る素地、土台があってのこと、小説では、宦官の陳公と銀細工師童七との結びつき、所謂“元手なしで利を得る”という商売が出現する。
「初め毎月二分の利子という約束で陳公から借りた元手は、それほど多くなかった。ただ借用したという程のことであるが、銀子は少々でも役に立つし、この陳公という名前があれば、侮る者などいないという寸法である。だから陳公に対してはごまかしもせず、節季ごとに利子を入れ、年毎に一たびは清算するというやり方で、この何年というものをやって来た。やがて陳公は一千両という銀子を出資して相棒として認めるようになった。元手が大きければ利益も多い。商売はいよいよ繁盛した。」(第70回P651)
地域で重要な手段として流通する貨幣というものが、自給自足の封建社会経済体制と真っ向から対立するという現実が社会のあらゆる面に出てきている、ということが小説から見てとれるのある。官位を買う、官爵を授かる、科挙の功名を漁り取る、裁判の断罪と和解、民百姓と官吏の関係、官吏と官吏の関係、人と人の関係、家庭における父と子、夫婦の関係、はたまた鬼神陰陽化け物の類いまでも、すべて、金銭が尺度となり、それぞれの関係を繋ぐ紐帯となっていることである。
「親戚知人友人もオレの知ったことじゃない、ただ知っているのは“銭”という一字だけである。相手に銭さえあれば、家柄もかまわなければ、顔見知りであろうがあるまいが、大喜びで親しい友人となって付き合う。」(河南本・第26回P245)
この台詞は、すでに、銭金というものによって、数千年もの間、守られて来た封建関係の土台が真っ向から揺さぶられていることを物語っているのである。作者がこの点を意識して書いたのかどうかにかかわりなく、このような表現描写は、かつての一連の歴史ものの小説の中にはまったく見られなかった。《醒世姻縁伝》が、中国の古代小説の中で、注目に値する長編回章小説であり、中国文学発展史上、間違いなく、重要な地位を占める作品であるという所以である。
因果応報という創作手法を使いながらも、作者は物語の筋、人物の登場からその人物の終焉末路まで、前後の交錯と曲折、どれをとってみてもみな終始一貫、前後呼応しており、それぞれが事細かに語られ、しかも文章に彩り潤いがある。こうした周到な脚色は、緻密に編み込んだ織物とでもいうべきであろう。
全篇、第22回までは、晁大舎を主軸とした悪姻縁の物語で、第22回以降は、狄希陳を主軸とした悪姻縁のそれである。この二つの悪姻縁の物語を、作者は前書きで、『前生において、強を以って弱を侮り、弱者のほうでは恨みを飲んで声も出さない。或いは、衆を以って寡を虐げ、寡者はただ黙り、敢えて誰何はしない、或いは、策を弄して財産を狙い、或いは奸計を以って命を陥れ、弱小者のほうは、その恨みをはらし、仇を講ずることも当時にあってはいきおい出来ない、というような二人も、今世に配されて夫婦になることがある』因果は必ずめぐり廻って来、互いに恨みを報い合うというのは、密接にしかも必然的に関係していて、読後、入って行けないような違和感を覚えるものでもなく、むしろその意図するところは珍しく優れていると云うべきであろう。ただ因果応報という骨組み構成が作者の意図、創作の考えに基づくという観点だけからいうなら、それは成功しているところと云える。しかし、各章個別には、散漫で締まりない個所もまま見られ、隔靴掻痒の感はまぬがれないが、人物描写については、以前の歴史物や小説のように飾り気のない客観事実のみを描くという、いわゆる線描手法と異なり、作者は特に人物の心理描写に主点を置き、それぞれ人物の持つ性格を使い分け、一群の典型的な人間像たちを作り出して見せてくれる。その描写たるや真に逼り、まるでその場に身を置くが如く、その人物を見るが如く、その声が聞えるが如くの筆力である。
例えば薛素姐である。彼女は希陳を虐めはするが、彼女自身もまた、方々、いたるところで人から貶され、辱めを受け、可哀相ではあるが、悍馬の如ききつい性格の女としても描く。狄希陳はどうか。視野の狭い世間知らずに、妓女にうつつをぬかす輩に、どこにでもいるヤボな俗物に、私腹を肥やすことしか考えない田舎育ちの男に描く。晁夫人はというと、寛大で包容力のある婦人に描く。貧しい人を助け、進んで善事を行う、見識は高く深い、ことの処置にはすべからく節度があるというように。童夫人はどうか。口上手で人をそらさない、ことの対処に周到で、知恵があり、「女にしておくにはもったいないような立派な女だね」(河南本・第71回P664)と陳公に言わしめるほどの女に描く。
無頼漢のあの汪為露はというと、卑劣で欲深く、陰ではデバ亀を決め込むようなふるまいをする男に描き、侯、張の両道婆や白姑子らは、やたら人の目を引くように己をひけらかすペテン師に描く。ひたすら己の俸禄と昇進だけを考えるあの晁思孝は、国家の安否など一顧だにしない貪欲鉄面皮の役人に描き、上は権力大の宦官から郷約や里正の下っ端役人に至るまで、民百姓を虐め、血税を搾り取るこうした官吏役人たちにも、それぞれに姓と名をつけ、しかもそれぞれに性格を持たせ、描き分ける。ともあれ、作者は、世の中にいるさまざまな人物像を描き出し、身分、経歴、環境を与え、各人の一挙一動、一語一句までが、その人物像とぴったりと重なり、実に生き生きとしているのである。
本小説の創作手法に、もう一つの特徴がある。それは墨をぶちまけでもしたように荒々しく書くかとおもえば、墨を惜しむこと金の如くで、一字一句疎かにせず描写する点である。時に厚化粧、時に薄化粧という濃淡のメリハリをつけている。厚化粧の時は、これでもかといわんばかりの重ね塗り的表現をする。しかし、薄化粧の時には、平板な表現でありながらも、さらりとした味わいのあるユーモアが読み取れる。また小説の中で、婦女の徳行、善行の道理を説き、宣揚する類いの文面については、くどくて無駄な描写のきらいもあるが、これも細かにみれば、どうして一本筋が通っていることが分かる。また性の描写については、多少興趣を添える程度には描かれている。このように全篇を通して論ずると、上述の如くであるが、ある章回では作者は同様にこの種の手法を使う。例えば、第24回で、作者は、崇禎年間に起こった幾つかの世相の一大事を僅か数語でその全容を表現して見せる。また、希陳と孫蘭姫については、始めの方では二人は影が形に添うように、いつも一緒に居て離れず、愛し慕われ、慕い愛されの関係描写に力を入れるが、後の方では、孫蘭姫が突然売られ、希陳は呆然自失、悄然として家に帰るのも忘れてしまう。作者は物語にこうした起伏を作り、最後には、天意の計らい、二人には僅かな時間ではあるが逢瀬の機会の依然あることを示唆する。それを作者は、非常に短い言葉で表現、恋愛の終結に含みを持たせ、大きな効果をあげてもいる。
また全篇を通じて、“妻には頭が上がらない”ことを堂々と描写する個所がすこぶる多いことである。ことに役所勤めの官吏らはほとんどが同病の士、恐妻家であるというところである。作者は、身辺の日常茶飯事に見られる小さなコトから、大局を見るように、社会全体の病いと官吏役人らの蒙昧、間抜け振りを殊更活写して見せてくれる。「呉刑庁、属僚らを考察す」のくだりである:
「われわれは全員鬚眉を立てたる一個の男子漢であるが、往々にしてご婦人に制せられておる。本日は天寒く雨まじりの雪である、一番諸君を考察しようと思う。これは官員としての考察ではない。諸君が女房殿を恐れているか、いないか、についての考察である。女房殿を恐れている者と恐れざる者の、その数どちらが多いかを調べて見ようと思うのである。」(河南本・第91回P857)
そして、この考察後に、画竜点睛ともいうべき次の結論を下すのである。
「この世の男で、女房殿を恐れんなどという者はいないようだ。陽は消え去り、陰の長生せる世の中、君子は小人を恐れ、活人は死鬼を恐れるならい、夫たる者何ぞ細君を恐れざらんや、だ」(河南本・第91回P858)
と。
次の例は、狄員外家の雇われ男、常功である。たまたま外科医艾前川から巻き上げた皮裏の上衣を身につけるが、脚の短い彼には似合うはずもない。ここで作者は「人はただ衣服を敬い、人を敬わず、というが、自分は、着る物さえ誰も敬ってはくれない」(河南本・第67回P631)という薄情な世間の有り体を批判するがために、誇張した手法を採る。まず常功の困り果てた表情状況を描き、そして主人の家の者に笑われる。それから、ごく自然に常功の口を通して上述の認識を引き出すのである。
本書で描かれる時間、場所、人物はそれぞれ異なるが、それらを文章に潤色する作者の手法は、正に当を得たもので、大波小波あり、大粒小粒の真珠あり、それらが絶妙に散りばめられていて、読後、ただ驚嘆するよりほかはない。
作者は山東省の方言を大量に使ってはいるが、正に行雲流水、文章によどみがなく、なめらかで、しかも生き生きとしているので、作品全体に生活の息吹と郷土色豊かな味わいが濃厚に流れ、作品に一層真実味を加えている。しかも、読む者に地域性とか時代の隔たりを感じさせもしないのである。人物像を作り上げるのに、言語というものが芸術上、どのようにサポートするものであるか、言語の口語化、方言がどのように作品中に使われるかなど、本書は我われに数多くの啓示を与えてくれるのである。
作品には、封建社会における重要なひとつの社会問題である「家庭と婚姻」が描かれているが、作者はこの問題をあの“家を整える”、家庭を平穏にすることを第一に考える儒教思想に基づいて解き明かし、片付けようとする。しかし、時代の制約か作者の世界観のなせるわざか、作品では、問題は宿命論に厳と存在するという観点から、因果輪廻の迷信思想をやたら宣揚する。一切が冥々裏に前世で按配され、人間の生死、善悪のすべて、因果応報から少しも逃れることが出来ない、と。作者の根底にあるこうした思想は、もとより陳腐な時代錯誤のシロモノではあるが。
更にもう一点、作者は作品の中で、官界の暗黒部分、官吏の腐敗と貪婪ぶりを赤裸々に暴露して見せる反面、苦しい境遇にある民百姓を救う清廉潔白の官吏のあることも期待する。しかし、作者自身、封建社会の中で生活する人間であり、また官界や科挙の試験に詳しく、ある程度功名のある人物であったろうと思われるので、作者の事件に対する毀誉褒貶、人物の功罪については、作者自身の封建道徳見解内での尺度評価であるに違いない。これも容易に小説中から見てとれることである。とまれ、現在の読者諸君にあっては、所謂“滓は棄て、美味しいところ取り”、歴史唯物史観的姿勢でこの作者と作品に接する必要があろう。
この他、作者は凡例の中で、「閨房、性描写については、多く書き連ねることはしたくなかった。淫猥な俗曲や猥褻卑語を多用すれば、読者に笑われ、本書の品位を落すことになり、低級卑俗な読み物の類いになってしまうからである。どうしても描写せねばならない個所では、極力抑え、添える程度に留めた。多用して、人から嘲笑され、個人の閨房秘事をあばいていると非難されては、私としては、恥ずかしく、なんともやりきれないからである。」とはあるものの、その低級卑俗な描写も、ときたま出て来るので、我われはこれらを削除せねばならないところであろう。
|