|
�����ɁA�g�������Ғ��h�Ƃ���B���́g�Ғ��h�́A�g����h�Ƃ͈قȂ�A�K�������̈Ӗ������߂��Ă���͂����B�ӓK�̍l�ɂ��A������ɂ܂��s�]��t�Ȃǂ̍�i������A��ɁA���̕�������Ƃɑ傫���c��܂��A���ҁs���������`�t�����Ƃ���B�������A���̎�̐��f�́A�܂������������ɉ߂��Ȃ��B��������֍֎u�ق́A�N��18�N�i1679�N�j�A�����40�̂���ɂł����{�ł���A���̌��30���N�ԁA���̒���ŁA�{�ɂȂ�����Ȃ��̂��L���Ă݂悤�F
|
�N��
|
22�N�i1683�N�j44�s���őS���t
23�N�i1684�N�j45�s�鋞�i���I���t����O�����������B�s�Ȑg��^�t
35�N�i1696�N�j57�s���Y�^�t�����L��
|
36�N
|
�i1697�N�j58�s���w�ߗv�t�땶����B�v�������O�S��\����I�сA���t���ās�v�������I�t�Ƃ��A�����땶�������B
|
43�N�i1704�N�j65�s���p�����t�����L��B
44�N�i1705�N�j66�s�_�K�o�t�����L��B
45�N�i1706�N�j67�s���M���t
48�N�i1709�N�j70�@���ĂɁs�Ė��v�p�t��ǂ݁A������菑������B
53�N�i1714�N�j75�@�s�Ϗې�߁t�O����������^�B
|
�@�ł���B�������āA�����Ɗ�����̔ӔN�̒���ꗗ�����Ă��A�s���������`�t���������\���͂Ȃ��B
�@���āg�Ғ��h�Ƃ����\���ł���B���́g�Ғ��h�Ƃ����Ӗ����l���Ă����ƁA�����͖{�����`������čs�����ߒ���T�邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B����̒��t���ł́A�������́A���łɏd�v�ȎЉ���̈�ŁA�l�X�̊S���ƂƂȂ�A����͕��|�`���ŕ\������A�����ň�ʂɍL�������̂��Ă����B����́s��ⳋL�t��\��Ɂs?���t�Ƃ����̂�����A���̒��ɁA�D�����A�������Ɋւ���̎���������Ă��邪�A����Ȃǂ́A���M�ƂɂƂ�A�đn�삷���Ŏg����܂��ƂȂ���ނƂȂ�B��҂́A���������`��n�삷��ߒ��ŁA�����炭�����������Ԃɓ`������ė����D�����A�������̕���Ɍ[������A�͂��܂��������s���Ă������{�A�e�����A���ȁA�����u�a�ɂ�����܂ŒO�O�Ɏ�ށA���W���A����₢�A�q�����킹�A�����n�������A�ҏW���Ȃ����A�����グ���ɈႢ�Ȃ��B
�@�ŋ߂̒����ŁA���Ìc22�N�i1817�N�j��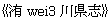 �̒��ɁF �̒��ɁF
�u䗎�ȁA���͉��A���c�S�N�����ɍ��i�A����2�N�i1574�N�j�b���̐i�m�c�c�l��̔n�A�������N�����B�n�A�I�ɓ��A�ɓ����B䗎�Ȃ͋͂����R���Ƃ��Ȃ��A������@�A���̕�������邱�ƂȂ��A�n�̐��ޓ��A�ɔ���A���⑾�ۂ�ł��炵�A���������B�n�瑯�R�݂͂ȋ���A�~����]�B䗎�Ȃ͍U�߂�̂��~�߁A�g�~������ΎE�����A�߂炦�̐g�Ƃ���̂݁h�Ɠ`�����B�w���������A���Ɩʒk�A���͂�����ō~�������B�l��̌R�������̏����́A䗎�Ȃ̌��т�������悭�v�킸�A���Ȃ������B���ׁ̈A������䗎�Ȃ𒃗ˑ���ɍ��J�����B��ɕ����E���Y�ɔC�����A�₪�ĕ������Y�ɂ܂ŏ��i�����B�v
�@�Ƃ����̂��������B���̋L�q������ƁA�������̊s���������s��ӂ̒n�A���Y�ƉG�T�̓y���������ԕ�����������ƕ������邱�ƁB�܂��A������53�N�i1788�N�j�ҁs�q�P�{�u�t�ɑh�����Ȃ�l���̋L�q�����邪�A���̐l���̏o�g�n�A���E���ׂāA���������L�����Ɠ����ł��邱�ƁB���̓�Ⴉ��A��҂́A�n���i�߂�ɂ�����A���ԕ��w�̒�����{�����z����鑼�A�����̐l�������Q�l�ɂ��āA�����グ�����Ƃ������ł���B����Łg�Ғ��h�Ƃ����̂ł͂Ȃ����낤���B
|